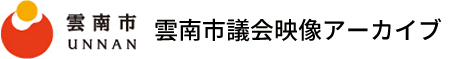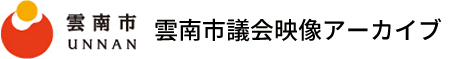人口減少、少子高齢化が叫ばれて久しくなる。市としても、地域を守るために、子育て支援、交流人口、関係人口の増加施策、Iターン・Uターン増加への施策等様々なことを行っている。しかし、現実的には、確実に少子化が進む中で、その子ども達がどのような教育環境で育っていくかが重要である。今いる子ども達、そして、将来生まれてくる子ども達は、地域の宝であり、日本の宝、ひいては、世界の宝といえると思う。その宝である子ども達を育てるのは、地域の教育である。そういう面で考えると、地域での教育の在り方は、将来の世界を左右するといっても過言ではないといえる。この、金銭面ではない、教育の質の魅力化が、雲南市の魅力化になり結果として、地についた人口政策になるのではないかと思う。
(1)市長は、学校の在り方について、「地域の拠点」「少人数指導の利点」「学校があることによる交付税のメリット」等を述べられ、積極的に統合することを否定しておられるように思う。しかし、将来の世界を担っていく子ども達を育てる教育のありかた、子ども達の無限の可能性を引き出す教育は、やはり、ある程度以上の集団での教育が必要であると考えるが、市長の見解を伺う。
(2)「日登教育」を進められた木次町の加藤歓一郎先生がおられた時の生徒の学力は、県内はもちろん、全国水準を超えていたといわれている。最近の雲南市の全国学力テストの結果は、どうであったか伺う。又、課題は何があったか伺う。
(3)現在、木次中学校の改築が計画されているが、教育設備には、ぜいたくな設備は必要ないと思う。知育・徳育・体育の概念を基本に、その力を十分に発揮できる設備が必要と考える。特に設備面において、将来の学校の魅力化と、現在の学校の魅力化をどのように考えておられるか伺う。
一般廃棄物の処理は、市民の「生活環境の保全と公衆衛生の向上」を目的に、市が責任をもって処理しなければならないとされている。しかし、市長は、本年5月の市議会全員協議会において、平成30年に必要性を言及されて以降6年間にわたって策定されてきた次期一般廃棄物処理施設整備構想を、財政上の理由から再検討することを表明された。この再検討の中には、処理業務の委託が含まれている。
(1)先日の報道で、京都大学のチームが、全国34か所の下水汚泥を分析したところ、すべての処理場から有機フッ素化合物(PFAS)が検出され、全国的に広がっているのではないかとのことであった。現在、国は下水汚泥の肥料化への推進を図っているが、もし、このPFASが雲南市においても検出されることがあれば、肥料化を断念し、1100℃以上で焼却することになると思われる。このことについて、下水汚泥の処理の現状とPFASに関する所見、又、PFASが検出された場合の対応をどのように考えておられるか伺う。
(2)今後、頻発するかもしれない、自然災害等により発生する災害ごみについては、現在はどのような対応をされており、今後はどのように検討されているか伺う。
(3)一般廃棄物の処理を他人に委託させる場合、その最終処分が終了するまで適正な処理を市の責任において確保しなければならないとされているが、この件については、検討されているか伺う。
(4)島根県内には、雲南地域の一般廃棄物を処理できる事業所は限られており、もし、この事業所が、火災、地震・津波、その他自然災害、不祥事等による業務停止、倒産等が起こった場合の対応をどのように考えておられるか伺う。