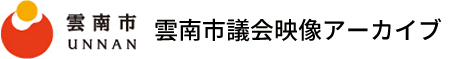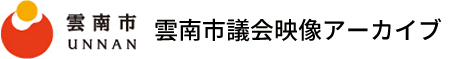(1)今年の5月、慶應義塾大学・京都大学の研究で図書館や図書館の蔵書数が多い自治体ほど、その自治体の要介護高齢者が少ないことが報道発表された。平成25年をベースに要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者7万3138人を対象に令和3年3月まで追跡調査をされ、各自治体の図書館の蔵書数と要介護リスクの関連を検証、その結果、図書館の蔵書数が人口当たり1冊増える(千人の町なら千冊)と、その地域の高齢者の要介護リスクが4%減少することに相当する相関関係が確認された。同様に10冊増えると約34%減少、さらに街に図書館が1館増えると、要介護者が約48%減少することが確認された。こうした相関関係が示された背景として、図書館が文化活動に参加することを可能にする地域の文化資本であることや、知的な刺激を受ける機会を提供していること、さらに高齢者の方が図書館に出かけることで身体活動も促進している点などがあげられた。また、図書館は無料で利用できることも大きいということだった。こうした結果をふまえ、あらためて、図書館の存在を検証すべきと思うが、市としては、図書館の価値をどのようにとらえておられるか伺う。
(2)現場からは、決められた予算内では、本が古くなっても入れ替えができないという声があがっている。図書館には様々な役割が課せられているが、図書があることが一番の柱と思うが、図書整備についての予算は適切か伺う。
(3)図書館では、読み語り、ストーリーテリングの会など様々なイベントも開催されている。イベントやボランティアの打ち合わせ、職員研修などで、木次図書館の視聴覚室を使われることが多いと聞くが、図書館の閲覧室のエアコンが壊れ、視聴覚室のエアコンと切り替えて使っているので、視聴覚室が夏場、冬場に使えないとのことだった。使っておられた市民の方からも苦情があがっている。また、加茂図書館もエアコンが壊れたと聞いた。空調の修繕のめどはあるか、対策について伺う。
(4)来館者の利便性向上を目的に、Wi-Fiのサービスを行っている図書館もある。大東図書館は無料でWi-Fiを利用することができるようだ。GIGAスクールで1人1台タブレットの時代、どの図書館でも同じようにWi-Fi環境を整える必要があると思うがいかがか。
(5)図書館の大切な業務の1つにレファレンスに関する業務がある。レファレンスとは、利用者の問い合わせに応じて、図書の照会や検索をする業務。郷土資料の質問もよくあるようで、何日もかけて所蔵や資料の調査をする業務を、多いときでは日々3件程度かかえておられるとのことだった。合併前の資料があまり残ってないようで、情報を残しておかないとすでに昭和終りから平成の始めの資料が少なく、分からなくなってきているとのこと。いずれ歴史になる資料となり、学校の授業でもいかせる。市として、情報収集し、各町でつくられた町史などをまとめ、昭和終りから平成の衣食住を盛り込んだ雲南市史を作成されてはと思うがいかがか。
(6)コロナ禍や読書バリアフリー法の制定、ICT技術の進歩など、図書館のDX化がすすんでいる。AIでの蔵書管理、書架点検、オーディオブックサービス連携、セルフ貸出機、利用者カードのデジタル化など様々なDX化があると思う。雲南市内での図書館のDX化についての状況、また今後の展開について伺う。
(7)必要なDX化はすべきだが、紙の本の価値について見直されている。スマートフォンやタブレットでは、検索で自分の見たいもの、同じ価値観のものばかりを見てしまうというデメリットがある。図書館は、自分が調べたいもの以外で気になる本のタイトル、色、形、ふと目にはいる存在感など偶然の出会いがある。また、図書館は、地域のしがらみなく、いつ誰が来ても詮索されることなく、無料で無記名で使える。最初に述べた図書館の数や蔵書数と要介護リスクの相関関係などもふまえ、今後の図書館について市としてどうして行く予定か。建物も古くなった施設もある。市内3つの図書室と3つの図書館について、ハード面・ソフト面について伺う。
(8)市政への提案箱で、令和5年度に移動図書館の開設についてご提案があった。「子どもたちにもっと本に触れて欲しいです。雲南市内は広いにも関わらず、図書館は大東・加茂・木次にしかありません。私の勤務する場所の近くは学校も廃校になり、図書館がありませんし、子どもだけで図書館に行くことはできません。移動図書館などで定期的に市内を回って、子どもたちに本と触れ合う機会を設けることはできませんでしょうか?子どもだけではなく、大人も本と触れ合い、自分を見つめる機会を持つことやその姿を子どもに見せることが大事だと思います。「飛び出す図書館」お願いしたいです」との提案。市の回答として、「ご提案いただきました件につきましては、東日本大震災をきっかけに移動図書館車等の移動図書サービスが再評価されてきていると認識しております。雲南市におきましては、移動図書館車は持っておりませんが、より身近な場所で臨時的に図書に触れる機会を作るため、事前に登録いただいた団体(地域自主組織や社会福祉団体のほか任意のグループでの登録も可能です。)に図書をまとめて貸出すサービスも実施しておりますので、こうしたサービスを活用した出張ライブラリーの開催についても、ご検討いただければと思っております。また、主にこども園等に出向いての読み語りも実施しております。今後ともご提案ご要望等ございましたら教育委員会、図書館等にお伝えいただければ一緒に検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。」と、あった。現在も出向いての出張図書館のような活動はされているとは思うが、図書館に公用車がないと聞いている。今後移動図書館の検討やこのような活動を継続していくためにも公用車は必要かと思うが、いかがか。
(9)図書館業務を担う人材が大切であると考える。島根県内で図書館の運営は直営、委託とあるが、雲南市は委託。委託期間は3年間。ノウハウがない事業所が選ばれれば、図書館の機能が十分にいかしきれない可能性がある。令和7年5月2日に、大阪市立図書館で、中央図書館窓口等委託事業者の交代に伴う業務の停滞についてお知らせがあった。受託業者が交代したことで、予約された図書等がなかなか渡せられない、返却された図書を所定の位置に戻せないなどの状況が起こった。蔵書の知識や職員の経験の蓄積、地域のことも知っている人材でなければ、図書館の機能はいかしきれない。現在の委託の職員配置体制は適切か、状況を伺う。