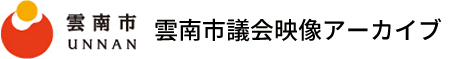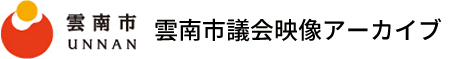国の農業政策において、これまで、地域との話し合いにより、「人・農地プラン」を作成・実行されてきたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されている。農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取り組みを加速することが喫緊の課題とされている。
この課題を解決するために、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地の利用を明確化する「地域計画」を定め、これを実現化するため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等をするという方針が示された。
この「地域計画」は、「地域農業の将来の在り方」と「目標地図」を明確にすることにより、農作業がしやすく、手間や時間、生産コストを減らすことが期待できる農地の集約化等の実現に向け、将来、「地域の農地を誰が利用しどうまとめていくのか」「農地を含め、地域農業をどのように維持・発展していくか」を、若年者や女性を含む幅広い意見を取り入れながら、地域の関係者が一体となって話し合い、次の世代に着実に引き継いでいくことを目的としている。
(1)2025年3月31日までに「地域計画」を策定、公表することとなっていたが、どのようなステップを踏み作成したか伺う。
(2)雲南市には、農地面積が4,756㌶あり、耕作可能な農地はその内3,643㌶(76.6%)となっている。地域計画では、どのような範囲をその区域としているか伺う。
(3)再生利用困難な農地及び遊休農地は、農地面積の内23.4%を占めている。これらの今後の利用について、どのように考えているか伺う。
(4)現在の農業を取り巻く環境の中では、時代に合った、農地の在り方が必要と考える。地域住民とよく将来のことを考え、農地とするところや、宅地とするところ等、地域計画に入れるべき範囲をもう一度、再構築すべきだと思うが、見解を伺う。
(5)公表された地域計画によると、雲南市の農用地の集積率は、計画単位ごとに、0.6%~81.0%とばらついており、25の計画区域の内、1区域81.0%以外は、すべて38%以下となっている。又、これら24の区域の10年後の目標集積率は、すべて、67%となっており、この目標を達成するための道筋をどのように考えているか伺う。
(6)島根県の報告によると、令和6年3月末時点の、県内の市町村ごとの担い手への集積率は、雲南市が16.9%となっており、知夫村の0%を除き最低となっている。これは、平成24年以来取り組まれた「人・農地プラン」による中心経営体に農地を集積していく将来方針が実施されていなかったのではないかと思うが、どう考えられるか伺う。
(7)雲南市の森林面積は、土地面積の78.7%で、農地面積は、8.6%である。又、その耕地面積は、島根県内の市町村の中で、4番目に広い面積を有している。1番目から5番目の市町の耕地面積の合計は、島根県全体の耕地面積の61.5%を占めており、島根県の農業において、雲南市は、大変重要な位置を占めていると思う。雲南市の農業は、中山間地域ではあるが、今回策定された「地域計画」を今後、改善しながら、しっかりと推進していかなければならないと思うが、見解を伺う。
令和7年3月定例会において、中小零細企業への支援、事業承継、新規起業支援、労働力不足への対応の一般質問を行った。又、「第3次産業振興ビジョン」も策定され、令和7年度から令和16年度までの方向性が示された。この中で、業種別総生産額を見ると、高い順から、製造業、不動産業、建設業、卸売業・小売業の順となっており、産業別従事者数でも、製造業、医療福祉、卸売業・小売業、建設業の順となっている。これら商工業の現在の課題は、これまで継続されてきた事業の持続的発展と起業及び新規事業への展開が必要で、そのためには、労務費を含む諸物価高騰に対応するための適正な価格転嫁、生産性を高めるための合理化と労働力の確保、円滑な事業承継が必要と考える。
(1)この度、「改正下請法」が成立し、又、令和5年には、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が出されている。いわゆる下請け企業や、中小零細企業が多い雲南市の事業者に対して、適切な価格転嫁をするような働きかけができているかを伺う。
(2)生産性を高めるための合理化と労働力の確保のためには、事業所の魅力化と利益の出る構造、賃金の上昇が必要と考える。最低賃金の引き上げには、国の関与を強めて支援するとの報道もあるが、どのように関与していくか伺う。
(3)市においても、団塊の世代が、これまで事業所を支えており、今後5年から10年でリタイアされることが目に見えている。8年前の2017年のアンケート結果を見ると、回答した事業主は、60歳以上の人が66.2%であること、又、「承継を考えていない」「廃業を検討している」事業所は、合わせて全体の60.2%もあり、さらに、後継者を決めている事業所の88.3%が、「子供などの親族」となっており、現在、増加している第3者承継は、あまり考えていなかったことがうかがえ、大変危機的な状況と考えられる。早急に、再び、現状を把握するためのアンケートを取り、特に優良な事業所については、確実に第3者継承を含む事業承継を行っていかなければならないと思うが、どのように考えるか伺う。
(4)雲南市は、産業振興のための様々な補助金・助成金を出していると思うが、その実績をできる範囲で公開し、その利用促進を図り、市民の理解を得ることが重要と考えるが、市としての見解を伺う。
令和7年2月、令和7年度~令和11年度の5年間の雲南市中期財政計画が示された。この中で、継続される収支不足、基金残高の減少、高止まりする市債残高、実質公債費比率の上昇等、厳しい財政状況が示された。市民、市職員、そして、議会もこの厳しい財政であることをほぼ認識しており、市の将来に不安を感じている状況と思っている。
(1)市長は、現在の厳しい財政になり、今後もこの状態が続く状況になった原因をどう認識しているか伺う。
(2)第3次雲南市総合計画において、その将来像を「えすこな雲南市」とされており、この「えすこ」を「丁度よい状態」と説明されている。「丁度よい」という言葉に危機感を持っており、いわゆる「ゆでガエル」にならないようにしなければならないと考えている。人口減少社会においても、市民が将来にわたって、「幸せに感じる」ためには、健全な財政状況が保たれるという状況を早急に示さなければならないと思うが、市長の見解を伺う。
(3)重要な財政指標の1つである実質公債費比率が、18%を超えると、地方債の発行に、「公債費負担適正化計画」を作成し、総務大臣の許可が必要になる。すなわち、一定の制限がかかるということである。中期財政計画において、近い将来18%に限りなく近づく状況のなか、早期に改善しておかないと、毎年のように繰り返される自然災害等の緊急事態に、市民の安心安全を担保できないのではないかと思うが、市長の見解を伺う。
(4)5月26日に総務常任委員会に示された、令和5年度の「統一的な基準による財務書類について」で、住民1人当たりの負債額が、一般会計等で117万円と令和4年の類似団体平均の77.5万円に対して非常に高く、又、住民1人当たりの行政コストも82.4万円と同様に類似団体の61万円に対して高い値を示している。この2つの指標だけでも、負債を減らしていかなければならないこと、行政サービスの合理化が必要なことは、顕著である。本年度から、「行財政改革推進課」へ改組されたが、財政再建と行政サービスの合理化は、痛みを伴うもので、これについては、ボトムアップではなく、トップダウンにより方向性を示し、住民の理解を得たうえで、強力に推進すべきだと思うが、市長の見解を伺う。
(5)今後、人口減少社会において、学校や交流センター等の公共施設の再編、行政サービスの棚卸による徹底した「ムダ」の排除が必要と考える。企業経営においては、収入は不安定な要素があるため、経営が厳しいときは、新たな投資は控え、建物、設備、機器の長寿命化、経営内の徹底したムダ取りと合理化にフォーカスして経営の安定に努める。このことについて、市長は、どのような方向性を考えているか伺う。
ご利用について
- この映像配信(映像および音声)は、雲南市議会の公式記録ではありません。公式記録は議会会議録をご覧ください。
- 映像配信を多数の方が同時にご覧になった際に、映像が正しく表示されない場合があります。
- 本サイトで公開している全ての情報について、複製・改変・配布を禁止します。